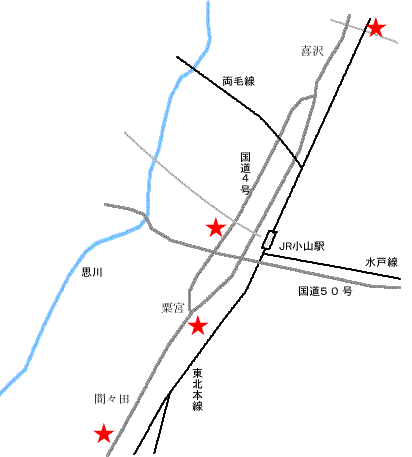 星印をクリックすると写真と説明が表示されます。
星印をクリックすると写真と説明が表示されます。
几号水準点は、東京釜石間の水準測量のため、ほぼ奥羽街道に沿って設置されています。
参加記
2002.2.11一部修正
「ミニミニ歴史館」講座 (第一回) 2002年1月20日、栃木県小山市立博物館
講師 同館職員 藤貫 久子さん
調査の際、私のつたないホームページをご覧になったのがきっかけで開催について教えていただきました。さっそく地元の池澤さんをさそって出かけました。
講演内容・・・ 水準測量の説明(レベル使用)、几号水準点設置の歴史的背景、市内に現存する几号水準点、一等水準点の紹介(スライド)
おことわり・講演とレジュメをもとに、趣旨を変えないよう編集していますので、以下の文責はwebmaster松村にあります。
・ ()内の日付は、藤貫さんが実地調査された日にちです。
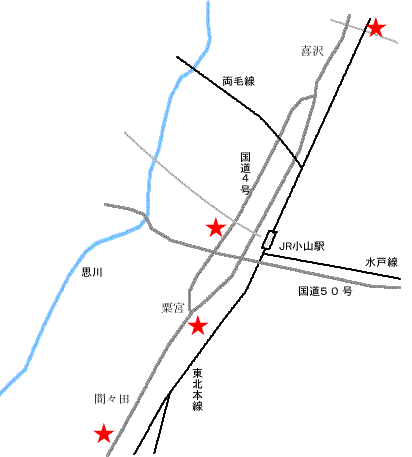 星印をクリックすると写真と説明が表示されます。
星印をクリックすると写真と説明が表示されます。
几号水準点は、東京釜石間の水準測量のため、ほぼ奥羽街道に沿って設置されています。
奥羽街道は江戸五街道として整備されてきました。江戸から宇都宮までは、日光街道と重なっていました。講演では、日光道中分間延絵図(東京美術刊昭和62年)を参考にしています。陸地測量部の迅速地図などの旧図があれば、現在の様子と比べてみてください。
几号水準点の設置順(東京の霊岸島から北上)により、日光街道を北上する形で紹介されました。
(2001年12月8日)
(2001年12月8日)
(2001年12月7日)
(2001年12月7日)
さらに市内の一等水準点を同様に国道4号を北上して紹介されました。
基準点コードでいうと2032から2040が該当します。2038と2040は亡失しているか所在不明です。
中には個人のお庭にあって、スコップで掘り当てたものなどもありました(2034)。
また、鋳物製のめずらしいふたのものがあったので、私も後で訪ねてみました。
基準点を探していて、「あった!」という喜びの他に、近くの方と昔話をしたり、教えていただいて人情を感じたりする時が楽しく、ありがたく思う時があります。
講座に参加された方々にもそんな楽しさが感じられたのではと思います。藤貫さんはじめ小山市立博物館のみなさま、ありがとうございました。
講演後、藤貫さん、先輩の平田さんとお話しした中で、几号の文化財登録の可能性についてお尋ねしました。
指定文化財となるには資料をそろえて審議会にかけるため、さらに調査が必要であること、また明治という時代がまだ新しいほうで(確かに)、几号も複数存在することなどから、
まず指定されるためのエントリーに時間がかかるでしょうとのお話でした。
しかし小山の場合は、几号の刻まれたものが信仰の対象などということもあり、さらに地元の方の気配りがあって、位置が変わっただけですべて残されています。几号として意図的に
残したものはないですが、当面は現状が大きく変わることはないのではと思います。